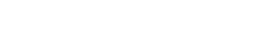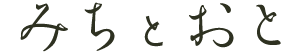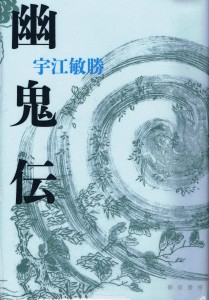中辺路在住の作家、宇江敏勝さんの小説『幽鬼伝』を読んだ。
全9編からなる短編集で、読みだしたら止まらなくなって一気に。
少し前の古道歩きで通り過ぎた、道湯川や道ノ川を舞台とした作品がとりわけ印象深かった。
道湯川が舞台となっているのは「権七太鼓の夜」という短編で、盆踊りの様子も鮮やかに描かれている。
昭和30年頃、道湯川から人々が去りはじめ、廃村が決まった頃のこと。最後の盆踊りの夜、闇の隙間から太鼓打ちの名人だった権七の亡霊が現れる。ラストシーンはまるで映像のように目に浮かび、踊りに興じる村人たちの地面を蹴る音や掛け声、跳ね回る太鼓の音まで聴こえるようだった。
道ノ川を舞台にしたのは「残された心」という短編で、主人公は道湯川に家を借りて山仕事をしている青年。峠を越えて、道ノ川の病弱な女性のもとへ夜這いに行くところから物語は始まる。
二人の恋は淡すぎて実るまでもなく、青年は故郷を出て都会に働きに行く。女性の心にかすかな灯りをともしたままで。
数十年後、初老となったかつての青年が道ノ川を訪れてみると、集落はすでに廃墟…。
その時ふと、女性が亡霊となって現れるのだ。
興味をひかれたのは道ノ川の廃屋の描写である。宇江さんは、この家を取材して書いたのではないかと。現地で私が見たような一升瓶も出てきたし。
小説の中で「せめて集落があったことぐらいは、板に書いて立てるべきだ」と、主人公の気持として書かれているが、私も願う。せめて熊野古道沿いの廃村には案内板があってほしい。古道歩きの人たちが、何も気づかず行き過ぎるのはあまりに切ないので。
他にも、富山の薬売りと炭焼きの老夫婦の話「おきぐすり」などもよかったけれど、心ひかれたのは「松若」。中辺路に伝わる民話を元に書かれた短編で、私はずっと、この民話が気になっていたのだ。
どういう民話かというと…。
松若は、はるか昔に兵生(ひょうぜ)という山里に生まれた男の子。
生まれた時から体が大きくて大喰らい。
家にいたら家族の分まで食べてしまうので、いつしか安堵山の奥に隠れて暮らすようになった。
山を駆け回り、獣や鳥をとって食べるうちに、やがて不老不死となる。
その松若がときおり、塩をもらいに里にやってくる。
快く塩を分けてくれる里人に感謝して、「なんど困ったことがあったら、わしの名をおがれ(叫べ)」と松若は言う。
「兵生の松若」には、いろいろな類型があるのだが、山で暮らしている大男が塩をもらいにくるところは共通している。資料によると、滝沢馬琴も『玄同方言』の中で、熊野の異人話として記しているそうだ。
十津川の樵夫(きこり)らが木を伐っているところへ、ある日羅刹のようなみなりの者がやってきた。髪はぼうぼうにのばし、腹にはけだものの皮をまとっている。斧を持って構えていると、男は「怪しいものではない。私も人間だ。塩を貰いにきた」と言うので、樵夫らもやっと心を落ちつけ、「塩はやるが、その塩を何に使うのか。お前はいったい何者か」と尋ねると、「私はもともと熊野の山里の者だ。十八の時、両親や親類のものが皆死に果てたので、山の中で生活している。鳥や獣を捕って命をつないでいるが、ときどき塩気のものを取らなければ生きていけない。そのため、山仕事をしている人を見つけては、こうして塩を頼むのだ」と答える。
それで、持ち合わせの塩を二合ほど紙に包んでやると、喜んで礼を言うので、「その塩でどれくらいもつのか」と重ねて尋ねると、四、五十年はもつという。それで「お前はいつの時代に山に入ったのか」と聞けば、「年号ははっきりしないが、嘉永(一四四一~一四四四)とか文安(一四四四~一四四九)とかいっていた」と言い捨てて、そのまま奥山へ消えていったーーという。(『熊野中辺路 歴史と風土』より)
滝沢馬琴は、「羅刹のようなみなりの者」の名を書いていないようだが、この男もまた松若だろう。きびしい山里の暮らしに耐えてきた人々は、深い山の奥で孤独に生きている人間を想像し、ふと心を寄せることがあるのかもしれない。たぶん、宇江さんも。
数百年の間、松若の名を語り継いできた里の人たちも去り、兵生も今は廃墟となっているそうだ。